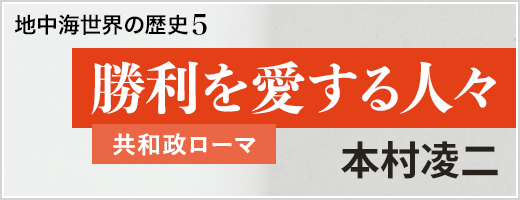落葉樹は、いうまでもなく晩秋には葉を落としますから、秋や冬の初めは、落ち葉を掃き集めるのが大変なわけですが、常緑樹も葉が新しくなる春には、冬を越した古い葉を落とします。ですから「春落ち葉」という表現もあるくらいで、我が家の「やまもも(山桃)の木」や「もち(黐)の木」、それに「金木犀」などがまさにそうです。金木犀は、秋口に小さな花を一斉に開いて香りが強く漂うことで知られていますが、山桃や黐の木は、この春先に花をつけて、特に雄の木の雄花が花粉を飛ばすためにできるだけ多くついて、それが花粉を飛ばした後に一面に散り敷きますから、この細かな花殻を掃除するのがまた一仕事です。
春先に黄緑の小さな花を一面に落とす黐の木は、かなり大きくなる常緑樹で、東日本では普通は庭木でしょうが、西日本では自生しているのだそうで、特に紀伊半島が自生地として有名で、江戸時代以来、樹皮からは「とりもち」を作っていたそうです。とりもちといっても、すぐに分かる人は少ないかもしれませんが、かつては蝉や蜻蛉など虫取りをするのにも、棒の先にネバネバする「とりもち」をつけてしたものでした。もちろん子供の遊びだけではなくて、いろいろ道具などを作ったりの職人作業にも、活用していたそうです。この黐の木には雌雄があって、小さな実が秋口に赤くなる頃には、鳥たちがやってきて盛んに食しています。雌の木には春にもまだ実が残っていることもあって、吉祥寺ですと、大きい鳥はヒヨドリや野鳩、小さいのだと目白(メジロ)や四十雀(シジュウカラ)といったところでしょうか。最近は界隈の樹木が減ってしまっているせいか、かつては群れでもやってきた尾長(オナガ)や椋鳥(ムクドリ)などは、ほとんど姿を見せないようです。かつては、コサギなども飛んできて、びっくりしたことがありますが、これは井の頭公園の池が近いからでしょうね。今は、花の落ちた後の黐の木が、新緑の黄緑が陽光にキラキラと、窓の外で眩しく輝いています。

秋口に実を一杯つけた黐(もち)の若木
山桃の方は、雄の木に、小さな赤褐色の花がびっしりついた長細い形の花群が、いくつもの枝にいっぱい付いて、その花粉が一斉に飛んで雌の木の花にとりついて結実してゆく、ということになるのですが、この花粉が飛ぶ様子は実は見たことがありません。それに雌の木の花も、どうやら小さくて葉陰に隠れているようで、私ははっきりとは見たことがないのですね。今年はなんとか見てやろうかと思っているのですが。でも不思議なことに、6月から7月にかけての初夏にもなると、赤褐色の丸っこい、粒々で覆われたような形の実がいっぱい、雌の木にはなるのです。強いですね、この木は。好きな人は、この山桃の実を食したり、梅酒のように果実酒にするそうで、きっと赤い綺麗な色のお酒ができるのではないかと想像されます。
拙宅の小さな庭には、ここで触れたような大きめの木だけでなく、草花も、家人が好きで買ってきてしまうものは、面倒を見るのは結局のところ私の役割となり、水をやったり花殻をつんだり、間引いたり。多年草は、しっかり越年しました。冬が乾燥して寒かったので、越年した草花や小ぶりの木々も、例年とは花をつけるタイミングがずれているものが多かったような気はしますけれど。それでも過酷な冬を越しますから草木は強い、というべきでしょう。いわゆる雑草も、どこから種子が飛んでくるのか、鳥などについてくるのか、すみれや水引草などをはじめとして、しっかり存在を主張しています。雑草なんて草は、人間がそう言っているだけで、本当はありはしないのですが。「門の草、芽出すやいなや、むしらるる」と詠んだのは、かの一茶です。さすが、ですね。
毎年、気候変動が激しくなって暑さ寒さが極端になっていることは間違いないようですが、地球上に草木がしっかり生き続けている限りは、生命の維持は草木が担ってくれるような気がしています。
著者:福井憲彦(ふくい・のりひこ)氏
学習院大学名誉教授 公益財団法人日仏会館名誉理事長
1946年、東京生まれ。
専門は、フランスを中心とした西洋近現代史。
著作に『ヨーロッパ近代の社会史ー工業化と国民形成』『歴史学入門』『興亡の世界史13 近代ヨーロッパの覇権』『近代ヨーロッパ史―世界を変えた19世紀』『教養としての「フランス史」の読み方』『物語 パリの歴史』ほか編著書や訳書など多数。