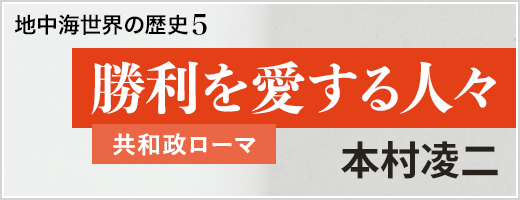昨年の秋口に、大気の寒暖の変化がまるでジェットコースターに乗ったみたいだ、と書いたのでしたが、今冬は、今度は豪雨や豪雪と小雨との両極端が日本列島を覆ったみたいで、特に吉祥寺界隈は、およそ雨の降らない、しかしめっぽう寒い冬が、3月になるまで長く続いた異例の冬だったと言えそうです。
気候変動の影響は、どうやら人の手には負えないくらいのところまで来つつある、と言えそうで、もう随分前から言われながら、世界のどこでも相変わらず対応は遅れ、あろうことかミサイルや爆弾で人殺しを繰り返す愚か者たちがのさばっているという、なんともはやの人間世界を眺めていると、どうしたって明るい気持ちには、なかなかなれません。そういう時には、老体は庭の草木の面倒を見ながら、その生命力の逞しさにホッとするのです。そして4月ともなると、少し寒気が緩んだ日には、今年も小さなヤモリの姿が窓ガラスの向こうに張り付いていたりするのを目にして、おお今年も生き延びて新しい命が生まれていたかと、嬉しくなるのですから単純と言えば単純ですね、我ながら。
昔から冬の終わりなどに「三寒四温」という表現があって、最近でもテレビの気象予報などを見ていると、この表現が耳にされることがあります。3日ほども冬の寒さが続くとしても、4日目には春到来を思わせる暖かな日が来る、それが繰り返されて春が近づく、という表現だと、私は思い込んでいたのですが、そして予報士の方の説明もそう言っているように聴けるのですが、本来は、ちょっと違う言い回しが元にあったのだということを、つい最近、この歳になって初めて知りました。やれやれです。その本来とは、冬の終わりが近づくと、3日ほども寒い日が続いた後に4日ほど暖かい日が続く、これでほぼ一週なわけですが、これが繰り返されて春が近づく、という言い回しが大陸の中国や朝鮮でかつてあって、これが日本では冬の季語の一つとなった、のだそうです。疑問なときには大きな辞書を見る、ということで広辞苑と大辞林とを見ましたら、まさにそう書いてあります。温かい日が多い方が、冬の寒い日々には有難いのですが、今年の3月から4月前半の様相は、どうも寒い日の方が多かったようで、そうなると本来の「三寒四温」ではなかったですね、少なくともこの界隈は、ということになります。
それでも、3月後半から4月にも入ると「木の芽時」、「きのめどき」ないし「このめどき」という表現がぴったりの時節になりますから、植物の生命力は強い、と、いまさらのように感心。自分自身が体力落ちて、体調も波乗りしているような日々を送っていると、余計のこと、面倒を見ている木々や草花の生命力に改めて惚れ惚れします。晩秋に強剪定して枝葉がほとんど少なくなっていた木にも、黄緑や少し褐色めいた彩りの混ざった新芽が小さく吹き出してきて、あれよあれよという間に葉の姿をとって緑を濃くする様相は、まさに生命力そのものを目の当たりにしている感動です。以前に、植え込みの間に勝手に生えて小さな木であった頃に移植してあげたら、いつの間にか大きく立派に育った山椒の木が、枯れたような枝に小さな芽をふく様子は、まさに「木の芽どき」という表現ぴったりに見えますし、冬の間には枯れ木になっていた紫陽花(あじさい)の老木にも、緑の芽が見えたと思ったら、またたく間に大きな葉へと広がっていく様は、毎年のことながらその生命力に感心するほかありません。
落葉樹は、いうまでもなく晩秋には葉を落としますから、⋯[続きを読む]
著者:福井憲彦(ふくい・のりひこ)氏
学習院大学名誉教授 公益財団法人日仏会館名誉理事長
1946年、東京生まれ。
専門は、フランスを中心とした西洋近現代史。
著作に『ヨーロッパ近代の社会史ー工業化と国民形成』『歴史学入門』『興亡の世界史13 近代ヨーロッパの覇権』『近代ヨーロッパ史―世界を変えた19世紀』『教養としての「フランス史」の読み方』『物語 パリの歴史』ほか編著書や訳書など多数。